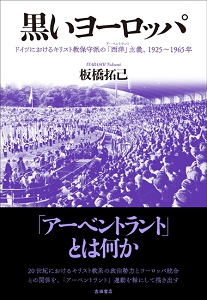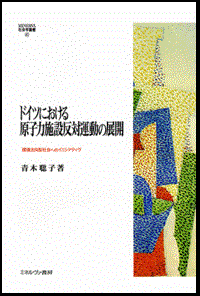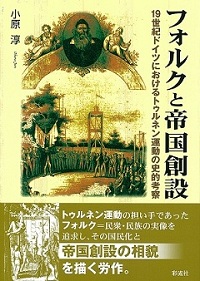≪2022年度日本ドイツ学会奨励賞≫
2022年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
|
| 選考理由 学会奨励賞選考委員会の西山です。本年度の選考委員会は昨年度同様、あいうえお順に、石田圭子幹事、板橋拓己理事、坂野慎二幹事、渋谷哲也幹事、三成美保幹事、弓削尚子理事、事務局を務める村上宏昭幹事と私西山の8名によって構成されており、不肖私が委員長を務めさせていただいております。 さて、今回、2022年度の日本ドイツ学会奨励賞は、森宜人さんの 『失業を埋めもどす ドイツ社会都市・社会国家の模索』名古屋大学出版会 に授与されることとなりました。以下、審査の経緯について、簡単にご報告申し上げます。 今回の学会奨励賞は、前回が例外的に対象期間を2年としたのに対し、通常通り2022年1月から12月の間に刊行された作品を対象とすることになりました。今回は4作品が推薦され、分野もそれぞれ異なることから、段階審査は設けず、直接全作品をそのまま全委員による査読の対象といたしました。 従来と同様、選考会議に先立って、各選考委員がそれぞれの作品に所見とともに10点満点で評点を付けたものを、事務局の村上さんの方で集計し、平均点を算出していただきました。それをもとに5月14日、オンラインによる選考会議を実施いたしました。そこにおいて、当日欠席した委員の所見も参照しつつ議論を行い、森さんの作品を奨励賞作品として暫定的に選出し、欠席の委員への周知と再考期間を設けたのち、異議はなかったため確定とし、事務局の村上さんより森さんに受賞の連絡をいたしました。以上の経緯は、先週6月11日の理事幹事会においても、村上さんから報告され、承認を得ております。 次に授賞理由についてご報告いたします。 森さんの作品は、タイトルにもあるように、失業という社会リスクがどのように歴史的に認識され、誰がどのようにそれを救済、予防すべく対応してきたのか、そしてこの問題が政治にどのような影響を与えたのか、ということを、このテーマにおける代表例ともいえるドイツの「長い20世紀」のなかで、その草創期ともいえる、世紀転換期から第一次世界大戦をはさみ、ワイマール共和国末期にいたる時期について論じられています。そこでとくに力点が置かれているのは、都市の役割であり、ハンブルクの事例などを中心に、ドイツの社会政策が「社会国家」のトップダウンとしてではなく、都市をはじめ非営利団体、専門家など、さまざまなアクターのイニシアチヴとその関係性のなかで織りなされるものであることを立体的に描き出されています。 本年2023年は、オイルショック50周年、ハイパーインフレ100周年、1873年恐慌150周年となります。これは偶然の符合に過ぎませんが、経済と社会、日常生活の関係性について、あらためて考える契機ともいえるでしょう。また、森さんが第3章で扱われたアフター・コレラのハンブルクにおける失業対策の模索などは、中央集権的といわれてきた日本における昨今の都道府県のコロナ対策でのイニシアチヴを否が応でも想起させ、社会政策の多元性について再考を促すものといえるでしょう。 選考会議においては、こうした現代の社会問題を考えるうえでもきわめてアクチュアルであり、また個人のアイデンティティにも大きな影響を与える「失業」という問題を、未公刊、公刊史料を駆使して重厚かつ堅牢に論じられた点が高く評価されました。また、ジェンダーなどの観点にも目配りがなされている点についても、学際的価値の高さが指摘されました。他方、カール・ポランニーに依拠する「埋めもどす」、「再埋めもどし」という本作品のキー概念について、門外漢にはやや分かりにくいという声もありましたが、授賞にふさわしい本作品の価値については、全委員の見解は一致しておりました。 最後に、受賞された森さんに心からのお祝いと今後のご研究の益々の発展をお祈り申し上げ、報告を終えたいと思います。森さん、まことにおめでとうございます。 |
| 森 宜人 氏の受賞あいさつ ただいまご紹介にあずかりました一橋大学の森と申します。このたびは、拙著『失業を埋めもどす―ドイツ社会都市・社会国家の模索―』(名古屋大学出版会、2022年)を日本ドイツ学会奨励賞に選出していただき誠にありがとうございます。ドイツ史家にとって無類の栄誉であり、拙著を推薦していただいた方々、西山委員長をはじめとする選考委員の先生方、そしてこれまでの研究生活を支えてくださったすべての方々に心より御礼申し上げます。 拙著は、19世紀末の失業の「発見」から両大戦間期の「再・埋め込み」へといたるプロセスを、ハンブルクを主たる事例として都市史の視角から描いたものです。失業の「発見」とは、失業が個人の自助努力ではなく社会全体で対処すべき問題であると認識されることを指します。「再・埋め込み」とは、K・ポランニーの「大転換」論でいう「脱・埋め込み」によって自律性を獲得し、社会から離床した労働市場とそれに付随する失業問題を、失業保険や、失業扶助、職業紹介、雇用創出をはじめとする一連の救済制度を通じて再び社会のなかに埋め込みなおそうとする試みとして定義しました。 タイトルの「埋めもどす」は、ポランニーの「大転換」論からヒントを得たものであり、失業を狭義の労働市場の問題としてではなく、市場経済を一構成要素として内包する社会全体の関係性のなかで捉えるべくつとめました。あらためて顧みますと、こうした着想にいたった源は、やはり一橋の学風に求められると思います。一橋の西洋史研究においては、ある特定の地域の実証分析を通じて、経済のみならず社会全体を綜合的に捉えようとする「文化史としての社会経済史」が志向され、「ヨーロッパとは何か」、「近代と何か」という根源的な―ある意味「しろうと」的な―問題意識より、市場経済の基礎をなす市民社会の歴史的意義が問われ続けてきました。なかでも私が影響を受けたのは戦後歴史学の旗手として知られる増田四郎先生の「市民的公共意識」論であり、学部学生時代に読んだ増田先生の『西欧市民意識の形成』(春秋社、1949年)が都市史研究を志す直接的なきっかけとなりました。 西山委員長より、「ドイツ研究として学際的な交流を推進するという学会の趣旨から」拙著が奨励賞の対象に選ばれたと伺いました。私の専門とする都市史は何よりも学際性を重視する領域であり、この点を評価いただけたことは感謝に堪えません。また、「文化史としての社会経済史」を標榜してきた一橋の西洋史研究の伝統の再評価にもつながりますので、学統の末席に連なる身として喜ばしいかぎりです。 ドイツ史に限らず、ヨーロッパ史研究の世界では長年、いわゆる人文科学系の西洋史学と社会経済史学の潮流の間である種のすみわけ的な状態がみられてきましたが、これを機に社会経済史研究の魅力と、奥行きの深さが広く認識してもらえることを願ってやみません。そして、何よりも私自身がこれからも多方面の関心を惹きつけられるような研究に取り組んでいく必要があります。今回の奨励賞はそのためになおいっそう刻苦勉励せよとの勧奨として身の引き締まる思いで受け止め、謹んで拝受したいと思います。 本日はありがとうございました。 |
≪2021年度日本ドイツ学会奨励賞≫
2021年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
|
| 選考理由 学会奨励賞選考委員会の西山です。本年度の選考委員会は昨年度同様、石田圭子幹事、板橋拓己理事、坂野慎二幹事、渋谷哲也幹事、三成美保幹事、弓削尚子理事、事務局を務める村上宏昭幹事と私西山の8名によって構成されており、不肖私が委員長を務めさせていただいております。 さて、今回、2021年度の日本ドイツ学会奨励賞は、坂井晃介さんの 『福祉国家の歴史社会学~19世紀ドイツにおける社会・連帯・補完性』勁草書房 に授与されることとなりました。 以下、審査の経緯について、簡単にご報告申し上げます。 今回の学会奨励賞は、昨年度総会においてご報告いたしました通り、掲示の不備のため、2021年のみならず、20年も含めた2年間に刊行された作品を対象とすることになりました。今回は当初5作品が推薦され、二段階の審査を行いました。第一段階として、各作品を分野の近い委員2名が査読する予備選考を行い、そのなかで2作品が本選考に残りました。それをふまえ、第二段階として、選考委員全員が2作品を査読し、従来と同様、それぞれの作品に所見とともに10点満点で評点を付け、事務局の村上さんの方でそれを集計し、平均点を算出していただきました。それをもとに5月13日、オンラインによる選考会議を実施し、5名の委員の参加のもと、坂井さんの作品を奨励賞作品として暫定的に選出し、欠席の委員への周知と再考期間を設けたのち、異議はなかったため確定とし、事務局の村上さんより坂井さんに受賞の連絡をいたしました。以上の経緯は、6月19日の理事幹事会においても、村上さんから説明が行われ、承認を得ております。 次に授賞理由についてご報告いたします。 坂井さんの作品は、ルーマンの機能分化論や自己言及システム論を批判的に援用しつつ、19世紀ドイツの政治や学術、労働運動や宗教における議論の中で、福祉国家における「社会的なるもの」の理念がいかに形成されたのかを、社会保険制度に焦点を当て、歴史社会学的に明らかにしようとするものです。 選考会議においては、研究史の記述が充実しており、研究動向をオリジナルな図にまとめて自身の研究視角を明確にしている点や、汗牛充棟の研究分野であるテーマでありつつも、個別要素に特化する、いわば「タコつぼ化」の動向に対し、理論と史料分析の両面から統合的な把握を試みている点が高く評価されました。その際、「補完性」や「連帯」といった、今日の福祉国家の問題を理解するうえで重要な概念を軸に議論している点も、射程の広がりを感じさせるものとみなされました。 他方、総じて言説分析が中心となっているなかで、高度に抽象的な議論が展開される部分が難解であるという声も聞かれました。また研究史のなかで一部見落としがあるのではないかとの指摘、さらに19世紀ドイツがもっぱらプロイセンを中心に議論されるなか、連邦制や都市自治など、ドイツ特有の政治の多層性の位置づけについての疑問、福祉国家におけるジェンダー的側面の欠落についての批判的な所見もありました。 しかし、学会奨励賞の意義に照らしてみれば、ここに示された福祉国家の歴史の立体的な見取り図は、著者坂井さん自身が展望するように、20世紀以降の展開や、今回のドイツの事例を出発点とした比較福祉国家論への貢献も期待させる内容であります。それは、付言すれば、私たちが現在経験しているコロナ禍をめぐる政治、学術などの多様なアクターの関係と、そこにおける「社会的なもの」の認識にもつながっているようにも思われます。 以上のことから、選考委員会は2021年度ドイツ学会奨励賞として、坂井さんの作品を選出いたしました。 最後に、受賞された坂井さんに心からのお祝いと今後のご研究の益々の発展をお祈り申し上げ、報告を終えたいと思います。坂井さん、まことにおめでとうございます。 |
| 坂井晃介氏の受賞あいさつ この度は拙著『福祉国家の歴史社会学』を2021年度日本ドイツ学会奨励賞という栄誉ある賞に選出していただき、誠に感謝申し上げます。奨励賞にご推薦くださった方や選考委員の先生方に、深くお礼申し上げます。僭越ながら、本書の初発の関心などについて少しお話しし、受賞あいさつとさせていただきます。 本書は、「社会的なもの」(das Soziale)と呼ばれる、近代社会における人びとの協働にかかわる規範的理念についての歴史社会学的研究です。 日本でも特に2000年代に入ってから、人びとの紐帯が希薄化し福祉や共助の仕組みへの限界や疑義が生じてきているという現状認識のもとで、主に思想的な視座から「社会的なもの」の理念が再注目されてきました。私は大学入学以後、こうした現代的な問題と理念の重要性に深く共感しつつ、「連帯」や「公正」といった「社会的なもの」の理念が学術的・哲学的には擁護・正当化されていく一方で、実際の社会生活の中ではむしろ煙たがれたり、政治過程ではほとんど無視されているような状況に疑問を感じておりました。 本書の基となった博士論文は、学部時代のこうしたやや素朴な問題意識が出発点となっています。そこからまず、ある規範的理念が社会に流通するようになるプロセスを考えるために、社会学、とりわけドイツの社会学者であるニクラス・ルーマンの社会学理論の研究を行ってきました。そこで得られた洞察は、特定の理念や考え方は制度のありようと無関係ではなく、境界を有した制度が複数作られることで、理念は制度間で異なる形で使われたり、部分的にのみ関連づけられたりされうるということでした。これは、西欧近代社会の成り立ちの一側面であるともいえるのではないかと思います。 そうした理論的関心のもとでのケーススタディとして、本書では1880年代におけるドイツ労働者保険の形成過程における理念の歴史的な分析を行いました。中でも、「社会」(Gesellschaft)、「連帯」(Solidarität)、「補完性」(Subsidiarität)という三つの語彙に着目しました。これまでの研究では、こうした理念は学術や労働運動、カトリシズムの語彙としてみなされ、そうした担い手の属性に注目した重厚な研究が蓄積されてきました。それに対して本書では、あえて同時代の政策過程に着目し、政治家や官僚たちが実際には、こうした語彙を新しく定義し直し、統治実践における「社会的なもの」として労働者保険の正当化に活用していったプロセスを明らかにしました。 本書のタイトルにもなっている「歴史社会学」の課題の一つは、こうした歴史研究を通じて現代的な問題の萌芽や由来を探ることにあります。本書で取り組んだ現代的な問題としては、政治と学術の分離と再関連化があるでしょう。一方で学術的知見は国家にとって一つの参照可能な資源でありつつ、他方で両者は自律的な制度としてみなされることが、いわゆる「価値自由」的な前提となっています。そうした前提が歴史的にどのように作られてきたのかを明らかにすることを通じて、現代のEBPM(evidence based policy making)のような、学知・学識が政治実践に与えるインパクト、あるいは国家による学術への恣意的な介入や活用について、適切な批判や評価が可能になるのではないかと考えています。 このように本書は、19世紀後半のドイツを対象にした歴史的な研究でありつつやや雑多な関心で書かれた領域横断的なものです。そのため社会学理論の系列でも、歴史研究の系列でも、はたまた福祉国家・社会政策の系列でも、うまく位置付けることができない——どの分野の研究者にも理解されづらい——ものになっているのではないかと自己認識しておりました。そんな中でドイツ語圏に関する学際的な学術研究を行うことを目的とされている日本ドイツ学会でこのような賞をいただいたことに驚きつつ、本当に嬉しく思っています。 本書は、選考委員会からの指摘にもあった通り、ドイツ歴史研究としては不十分かつ問題含みな点も多いかと思います。今後はそうした点を重く受け止め、比較に開かれた歴史社会学的研究という射程を維持しつつドイツ研究・歴史研究としてもより質の高い研究を進めていく所存です。どうかご指導ご鞭撻のほど、お願い申し上げます。この度は本当にありがとうございました。 |
 |
2020年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
に決定されました。2021年6月19日、オンラインで開催された日本ドイツ学会大会での授賞式において奨励賞選考委員会の西山暁義委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、濵谷氏に賞状と副賞が授与されました。 |
| 選考理由 2020年度の日本ドイツ学会奨励賞は、 濱谷(はまたに)佳奈さんの『現代ドイツの倫理・道徳教育に見る多様性と連携―中等教育の宗教科と倫理・哲学科との関係史』風間書房 に授与することとなりました。 以下、審査の経緯について、簡単にご報告申し上げます。 今回、奨励賞候補作品として査読対象となりましたのは、濱谷さんの作品を含め、合計4点でした。このことに関しまして、例年の通り、自薦および他薦によるものでしたが、募集にあたりまして、学会HPにおいて募集の呼びかけが更新されておらず、昨年度のままとなっていたことが、査読作品確定の段階ではじめて判明いたしました。そのため、近藤理事長をはじめ学会事務局ともご相談した結果、次回2021年度については、2020年に刊行された作品も候補となりうることとし、理事幹事会においてご承認をいただきました。この不備につきまして、学会奨励賞選考委員会を代表しまして心よりお詫びいたしますとともに、再発の防止に万全を期す所存でございますので、何卒ご容赦いただきますよう、お願い申し上げます。 さて、この4作品につきまして、本年度も7名の選考委員が査読し、それぞれの作品の評価を事務局に提出しました。評価は従来通り、各委員がそれぞれの作品に所見とともに10点満点で評点を付け、それを集計する形で行いました。その上で、5月30日、事務局村上さんを含め委員7名の参加によるオンライン会議での合議のうえ、受賞作として満場一致で濱谷さんの作品を選出いたしました。そのうえで、この結果を6月5日の理事幹事会に答申し、承認をいただき、受賞が確定した濱谷さんにご連絡を差し上げた次第です。 次に授賞理由についてご報告いたします。 濱谷さんの作品は、現代ドイツの公教育における「宗教科」と「倫理・哲学科」との関係性とその関係の歴史的変容を、それらの制度的地位、さらに実際のカリキュラム内容、授業実践という複数の観点から明らかにしようとするものです。世俗国家と宗教の相克関係はもちろんドイツに限られた現象ではありませんが、ドイツの場合、歴史的に宗派とも密接に関連した連邦制をとり、また宗教に否定的であった東ドイツを統合したという歴史的背景。そして、存在感を増すイスラーム移民や、歴史的経緯から人数は少なくとも重要な地位を占めるユダヤ教徒たち。こうした複雑な多様性をもつドイツにおいて、宗教と哲学・倫理は学校教育においてどのように位置づけられているのか。この重要な問いに対し、濱谷さんの研究は、法制度、カリキュラム、そして授業実践などの多面的にアプローチされています。そしてそこから、宗教間対話や多様な価値観の共存の実現へ向けて取り組む現在のドイツの努力と葛藤を教育という場所から浮かび上がらせたており、教育学という1つの分野にとどまらず、現代ドイツ社会とその歴史的背景に関心をもつ者全般に貴重な示唆を投げかけているといえます。こうしたことから、本作品は日本ドイツ学会奨励賞の趣旨に照らしてその受賞にふさわしいものであるとの評価で、選考委員会は一致いたしました。 なお、前に述べました通り、本年度の募集について不備がございましたが、濱谷作品に対する評価は、評点の平均からみても歴代の受賞作と変わらず、高いものであったことを申し添えさせていただきます。 最後に、受賞された濱谷さんに心からのお祝いを申し上げて、報告を終えたいと思います。濱谷さん、まことにおめでとうございます。 以上です。 |
| 濵谷佳奈氏の受賞あいさつ この度は、拙著『現代ドイツの倫理・道徳教育にみる多様性と連携−中等教育の宗教科と倫理・哲学科との関係史−』(風間書房刊)を2020年日本ドイツ学会奨励賞という栄えある賞に選定していただき、誠に光栄に存じます。本書をご推薦くださいました方々、選考委員会の先生方、これまでの研究生活でご指導を賜りました先生方、ドイツでの調査の過程でご協力くださったすべての方々に深く感謝申しあげます。この賞が「ドイツ語圏に関する学際的な学術研究」の発展に資することを目的として設けられたと知り、今後いっそうの精進を重ね、研究の深まりと広がりを目指して励んでまいりたいと存じます。 本書は、現代ドイツの中等教育段階における倫理・道徳教育にみられる「多様性」と「連携」という構造を明らかにすることを目的に掲げ、「宗教科」と「倫理・哲学科」との関係に注目し、そのあり方が1960年代のヴァチカン公会議以降どのように変化しているのかを考察しています。とりわけ、公立学校でありながら倫理・道徳教育が単純に「世俗化」されず、個々の宗派・宗教・世界観の尊重を貫いて特異なあり方が形成されてきた歩みを、多層的な分析を試みながら探ってゆきました。 ひとくちに「ドイツ」といっても決して一枚岩ではありませんので、これをふまえて本書では、「宗教科」と「倫理・哲学科」の法的位置づけが特徴的かつ対照的な四つの州の事例に焦点を当てています。日本語で書く論文としてやはり連邦全体を見通す必要性を重視したところ、予想以上に長い年月がかかってしまったという反省はあります。けれども、複数州における両教科の法的地位、カリキュラム、授業実践の三つの領域に注目することで、各州が各様に倫理・道徳教育のあり方を確立してきた様子が浮き彫りになりました。これによって、それぞれが「多様性」という特性をもつ宗派的宗教教育と世俗的価値教育という、大きく二つの輪郭をもつ倫理・道徳教育の複雑な関係性とその変容を描き出し、それが指し示す意味を考察するという道が開かれたのだと思います。 ドイツの倫理・道徳教育にみられる「多様性」と「連携」という構造の解明をとおして、本書で特に強調したいと思った点は、次の二点です。 第一に、ドイツの事例から言えば、近代公教育の一大特色とされる「近代化=世俗化=脱宗教化」という図式は基本法の制定期からすでに当てはまらない、という点です。ドイツ基本法は、キリスト教の宗派教育を公立学校で行うことを規定しつつも、その宗教科にわが子が出席するかどうかは、保護者が決定する権利も認めています。現在に至る宗教科とは、第二次世界大戦後のナチズムへの反省、第二ヴァチカン公会議、東西ドイツ統一といった歴史的文脈の中で、葛藤をくり返しながらその結果として出てきたものであり、「宗派教育」という枠組みこそ維持されているものの、そればかりを強化するものではありません。むしろ、世俗的価値教育としての倫理・哲学科との連携が模索されています。他方の倫理・哲学科においても、その教育内容では宗教科と目標を共有し、内容も共通する部分が多いと確認されました。このドイツの宗派的宗教教育と世俗的価値教育の特異性は、公教育のなかに、多種多様な宗派や世界観に由来する宗教性や倫理性の各々を、ある程度担保する形で持ち込むことが、倫理・道徳教育のひとつのモデルとして成立しうることを示唆していると考えられます。 第二に、各国が宗教や価値観など各種の多様性をどう尊重していくのかを考える上で、ムスリムの増加などによる信仰の多元化への対応を進めるドイツの事例が、格好の例を提供しているのではないか、という点です。日本では、教育基本法第9条が公立学校での「特定の宗教のための宗教教育」を禁止しているため、宗教による教育をどのように位置づけるかについて検討することが少ないといえます。同じように「宗教」や「道徳」といっても、教科としてのコンテクストも社会的文脈もドイツとは全く異なります。しかし、自他の宗教に関する理解や寛容は、宗教に起因するとされる軋轢や分断が生じている現代社会において、無くてはならない重要な基盤です。政教分離の原則を掲げているか否かに関わらず、学校教育のなかで宗教教育をどう位置づけ、どのように行うのか、また、宗教や価値観など各種の多様性をどう尊重していくのか、これらの問題をどのように解決していくのかという方策のあり方が問われているといえます。 最後になりますが、いくつかの書評で頂戴しました貴重なご指摘にお応えしていけるよう、また、日本とドイツの間の教育実践の交流に少しでもお役に立てるよう、さらに研鑽を積んでまいりたいと存じます。 この度は、本当にありがとうございました。 |
 |
2019年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
川喜田敦子氏(東京大学大学院総合文化研究科 准教授) に決定されました。2020年6月21日、オンラインで開催された日本ドイツ学会大会での授賞式において奨励賞選考委員会の西山暁義委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、秋野氏と川喜田氏に賞状と副賞が授与されました。 |
| 選考理由 2019年度の日本ドイツ学会奨励賞は、 秋野有紀さんの『文化国家と「文化的生存配慮」—ドイツにおける文化政策の理論的基盤とミュージアムの役割』美学出版 および 川喜田敦子さんの『東欧からのドイツ人の「追放」—二〇世紀の住民移動の歴史のなかで』白水社 の2作品に授与することとなりました。 以下、審査の経緯について、簡単にご報告申し上げます。 今回、奨励賞候補作品を選定する前段階として、本年度より選考委員会事務局を担当されることになった村上宏昭さんより、昨年度と同様、対象期間に出版されたドイツおよびドイツ語圏に関わる書籍のリストを選考委員会、および理事幹事会に示していただき、それと同時に奨励賞候補作品の推薦を学会員の皆様にお願いいたしました。 その結果、4作品が奨励賞候補作品として推薦されることになりました。うち1作品につきましては、本年1月、2009年度の深井智朗氏の奨励賞受賞取り消しに際し、今後学際性を維持しつつ再発を防止するための取り組みとして、学会HPにおいて報告させていただきましたように、「候補作品が、選考委員会がカバーする専門領域から外れる場合、学会の内外を問わず、可能な限り近接分野の専門家に調査を委嘱する」ということを実行いたしました。ここで鑑定を執筆していただいた方、また鑑定者の紹介にご尽力いただいた方のお名前を挙げることは差し控えさせていただきますが、ご協力に心から感謝を申し上げたいと思います。 さて、この4作品につきまして、本年度より6名へとスリム化した審査委員が査読し、それぞれの作品の評価を事務局に提出しました。評価は従来通り、各委員がそれぞれの作品に所見とともに10点満点で評点を付け、それを集計する形で行いました。その上で、5月31日、委員全員の参加によるオンライン会議での合議のうえ、受賞作2作品を決定いたしました。 最初に、秋野さんの作品にかんしましては、ドイツにおける文化政策がどのような歴史的背景の下に成立、発展してきたのかを跡付けたうえで、戦後の西ドイツ、そして「採算性」の名のもとに市場原理が文化領域により浸透するようになった統一以降のドイツにおいて、文化の「公共性」がどのように定義され、そして実践されてきているのかを主題とした、きわめて意欲的な研究と評価されました。「文化的生存配慮」をキー概念として、法制度、行政と、ミュージアムにおける実践の双方向からのアプローチは、議論に奥行きを与え、そこに示された民主主義社会と文化の関係のあり方をめぐるドイツの試行錯誤は、今回、新型コロナ感染症問題が図らずも露呈させた日本における文化の公共性の問題を批判的に考えるうえでも、大いに参考になるであろうことが、多くの委員によって指摘されました。 次に、川喜田さんの作品につきましては、「追放」という長くナショナリズム、一国史的枠組みのなかで語られ、研究されてきたテーマを、時間軸と空間軸を広く設定し、それがいかにヨーロッパ的次元のなかで構想、実行されてきたのか、また追放民たちの統合の複合的なプロセス、そして社会、学術における記憶や神話の形成にいたるまで、さまざまな側面を豊富な資料をもとに堅牢に論じた労作である、という点で評価は一致しました。ドイツ史をどのようにヨーロッパ、さらにはグローバルな文脈の中に位置づけるか、ということについては、近年さまざまな研究が行われておりますが、川喜田さんの研究は20世紀現代史にかんするその重要な例であり、「住民移動」をかく乱要因ではなく、むしろ重要な構成要素とする視点は、ドイツにかんする学際的なアプローチに大いに刺激を与えうるものである、と評価することができます。 以上、2作品とも、ドイツ研究の学際的発展に資する、という奨励賞の趣旨に十分にかなう研究であるという点について、選考委員会で意見は一致し、2作品同時受賞ということに決定いたしました。このことを6月6日の理事幹事会に答申し、承認をいただきました。 |
| 秋野有紀氏の授賞あいさつ 獨協大学の秋野有紀と申します。この度は、拙著『文化国家と「文化的生存配慮」』に日本ドイツ学会奨励賞という名誉ある賞を与えていただき、誠にありがとうございました。この場をお借りして、本書を御推薦下さった方、選考委員の先生がたをはじめ、これまでの研究生活でお世話になってきた全ての方々に、心よりの御礼を申し上げたく存じます。 本書は、ドイツの文化政策を扱っています。2000年代半ば、ドイツには、ボン基本法を改正し、国家目標を定める第20条に、民主的、社会的と並び、文化的を入れられるか、という議論がありました。そうなると、ドイツを「文化国家」と呼ぶことも可能になるわけですが、ここで大きな論争となったのが、本書のタイトルの文化国家と生存配慮でした。 文化国家には先進国という意味もあります。しかしある一時期、ドイツで、集権的かつ闘争的な用法が現れた時期がありました。生存配慮は、政策理念を実施する行政レベルの用語です。しかしこちらもナチ時代に、法に優越する権力を行政に集中させるための理論となりました。それゆえ今日でも、留保が付きます。 本書はこの2つを手掛かりに、3つの方向から、ドイツがどのような思いで、文化政策を形作ろうとしてきたのかを、探ってゆきました。1つ目は、近代国民国家揺籃期の文化振興法制化の意図、2つ目は、戦後西ドイツの文化政策理念の狙い、そして3つ目は、80年代以降、そうした政策理念を可視化していったミュージアム制度の意味です。 ナチ時代の過去の反省から、ドイツの文化政策の権限は、州と自治体にあります。しかし州であれ、自治体であれ、政治権力が芸術に介入する危険性は同じです。本書がドイツの特徴として、一番強調したかったのは、それを見越して、1970年代に「新しい文化政策」を始めるにあたって、批判的民主主義というものが、文化政策の基本に、なかば期待を込めて埋め込まれ、その上に今日の制度がある、という点です。 日本では、「ドイツも福祉に手厚いヨーロッパの国のひとつだから、自ずと文化予算が潤沢なのだろう」と思われがちです。けれども、ドイツではしばしば、「文化は、民主主義の基盤」であり、「文化政策は、(Sozialpolitikではなく)Gesellschaftspolitikである」ことが強調されます。つまり「自らの理性を公的に使う」という意味で批判精神を持った市民が、自らの手で、統制し、形作っていくことを重視する政治領域の一つと、理念的には、考えられています。こうした政策や、既存学問の批判的な問い直しという潮流が相互に影響を与える中から、ミュージアム論争や歴史家論争が、起こっていきます。 今日わたしたちはドイツのミュージアムで、多くのギャラリーガイドや音声ガイド、展示の説明を見かけます。議論を喚起するこうした仕事を担うために制度化されているのが、フェアミットラーです。もはやペダゴーゲと言われないのは、彼らが、来場者に作品の情報を教養として「教える」存在ではないからです。彼らは、既存の価値観や思考枠組を揺さぶり、分析視点の複数性を、住民と一緒に生み出すためにいる専門です。 さて最後になりますが、ドイツの政策立案では、基本中の基本としてBestandaufnahme、つまり、まず現状把握をせよ、ということが、口を酸っぱくして言われます。しかし私自身は、自分の関心のままに潜ったり、浮かんだり、回り道ばかりしています。本書でも、歴史や哲学思想に触れないと政策の背景が理解できない部分に関しては、その時々に学ぶよう努めては参りました。しかし、専門家の方々から見ると、理解が表層的で、間違いもあるかもしれません。この受賞を機に、本書が様々な分野の専門家の方がたの目に留まり、さらなるご批判を戴けましたら、大変有難く存じます。 本日は、貴重な機会を設けていただき、誠にありがとうございました。 以上をもちまして、私の挨拶に代えさせていただきたく存じます。 |
|
| 川喜田敦子氏の受賞あいさつ このたびは、昨年春に白水社から出版いたしました『東欧からのドイツ人の「追放」――二〇世紀の住民移動の歴史のなかで』に対して日本ドイツ学会の学会奨励賞をいただけることになり、大変光栄に思っております。先ほど、学会奨励賞選考委員会の西山委員長から、身に余る評価のお言葉をいただいたことにつきましても御礼を申し上げます。 この本のもとになる研究を始めたのは、1990年代の終わり頃のことです。被追放民の統合というのは、私が博士論文で取り上げたテーマでした。この本の後書きにも書いたことですが、論文を書き終えた後、すぐにも本にしたほうがよいとあちらこちらから言われながらも、私は、博士論文そのままの形ではどうしても出版することができませんでした。以来、20年近くかけて、このテーマをどういう形で世に問えばよいのかということを考え続けてきたことになります。 それは、修士・博士あわせて5年間という、人文系の研究者としては際立って短期間のうちに博士論文を書いて大学院を出てしまった私にとって、つまり、研究者として一人前になる前に修業期間を終えてしまったということを切実に意識せざるをえなかった私にとって、苦しい時期ではありましたが、大学院を出たからこそ、対象地域も方法も違う方たちと自由にいろいろなプロジェクトをご一緒できるようになり、少しずつものが見えるようになっていった、学びと成長の時期でもあったのだと思います。 20年のうちに、いつの間にか、後進を育てる身になりました。これほど時間をかけることを誰にも勧めはしませんが、これから研究者になろうとする若い世代が、どういう道を通ることになろうとも、自分なりの歩みを重ねて、いつか納得のいく仕事ができるようになる――その手助けをすることができればと考えております。 この本を書きながら、私のなかには3つの大きな関心が底流としてありました。第一に、歴史の記述としては、ドイツという一国史の枠組みを超えて、ヨーロッパ、さらにはアジアをも含み込むような大きな視野のなかで対象をとらえたいということです。これについては、この本のなかだけでは十分に実現することができませんでしたが、昨年11月に名古屋大学出版会から共編として出した『引揚・追放・残留――戦後国際民族移動の比較研究』という本のなかで、さらに一歩進めることができたかと思っております。 第二に、歴史の事象がどのように歴史の語りになっていくのかを、現実の歴史的文脈のなかで考えたいという関心もありました。何度か書評会を設定していただいたなかで、この点についてはあまり議論になったことがないのですけれども、実はこれが、もともとの私の問題関心の核です。戦後の国内情勢、国際情勢が、「追放」の当事者に対する統合政策だけでなく、彼らと彼らの経験をどう語るかも規定していく――東欧からのドイツ人の「追放」というのは、私にとっては非常に面白い素材でした。 第三の関心は、自分の扱う歴史的なテーマについて語ることが、今、自分の生きている社会と世界に意味をもつものでありたいということです。今回の本は、「ひとの移動」が大きな問題になったとくに2015年以降の情勢を踏まえて、「他者と生きる」ということを歴史の連なりのなかで考えようとしたものです。また、この本を日本で出版するということは、加害国の被害体験をどう語るかということが重要なモチーフになるということでもありました。 今、この本の後にとりかかろうとしている仕事は、少し違うテーマになりますが、根本的な関心には通底するものがあるのではないかと思っております。次のテーマにもしっかりと取り組み、また皆様のお目にかけることができるようなものにしたいと考えております。今回、学会奨励賞をいただけたことは、次の仕事の弾みになります。このたびは本当にありがとうございました。 |
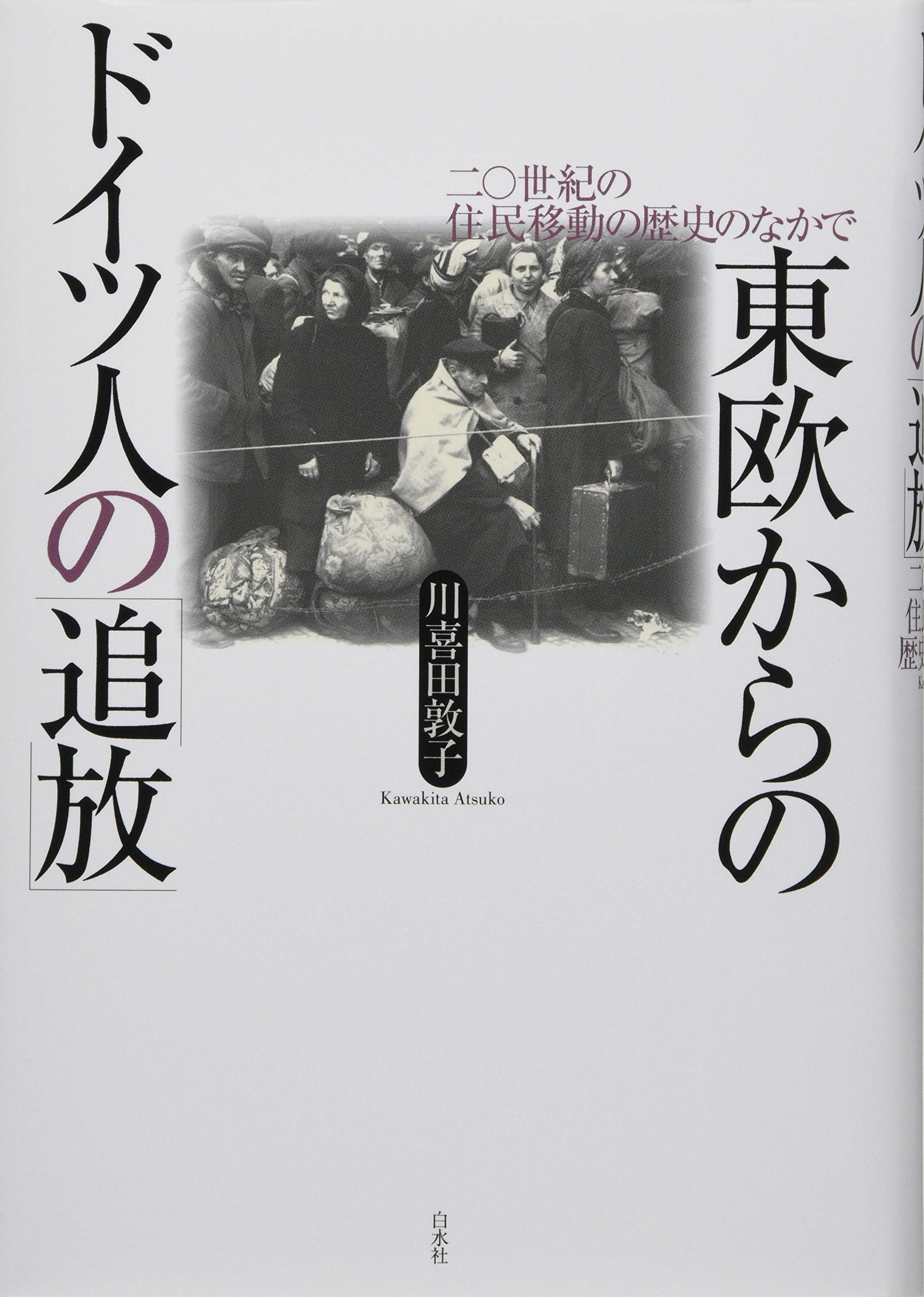 |
2018年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
に授与されました。2019年6月30日、法政大学市ケ谷キャンパスにおいて開催された日本ドイツ学会大会に際して授賞式が行われ、奨励賞選考委員会の村上公子委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会香川檀理事長から石井氏に賞状と副賞が手渡されました。 |
|
選考理由 2018年度のドイツ学会奨励賞は、 石井香江『電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか:技術とジェンダーの日独比較社会史』ミネルヴァ書房刊
に差し上げることになりました。
今回、奨励賞候補作品を選定する前段階として、奨励賞事務局担当の弓削さんから、対象期間に出版されたドイツおよびドイツ語圏に関わる書籍のリストが示され、奨励賞候補作品としての推薦を学会員の皆様にお願いいたしました。 その結果、4作品が奨励賞候補作品として推薦され、奨励賞審査委員6名ないし7名がそれらの作品を読み、評価したものを所見と共に事務局に提出しました。 作品によって所見を寄せた委員の数が異なるのは、各々の審査委員のやむを得ない事情によります。また、それによって不公平が生じないよう、評価の際には考慮いたしました。 評価は従来通り、各委員がそれぞれの作品に10点満点で評点を付け、それを集計する、という形で行いました。その上で、5月26日、出席可能な審査委員が集まって合議の上、受賞作を決定いたしました。 石井作品は全ての審査委員から非常に高く評価され、受賞に疑義があるとすれば、既にアカデミック・キャリアに乗っていらっしゃる方を対象とするのは、奨励賞として適当なのか?という点と、著者の年齢のみである、ということになりました。 第1の点は、これまでも既に大学で定職をお持ちの方に何度も奨励賞を差し上げておりますので、今回それを問題にする必要はないと考えられます。第2の年齢に関しては、本作執筆時には奨励賞の年齢制限内であったということで、クリアできるであろうと判断いたしました。
石井香江さんは、既にご存じの方も多いかと存じますが、同志社大学准教授でいらっしゃいます。そして、受賞作『電話交換手はなぜ「女の仕事」になったのか』は、膨大な人事資料をドイツ、日本双方について丁寧に読み込み、そのデータに基づいて、「電信」「電話」に携わる男女の就労者の生活を描き出し、電話交換手=女というイメージ成立の裏にある歴史を日独対照しつつ明らかにしようとするものである、と纏めることができるでしょう。 本作は本年5月、昭和女子大学女性文化研究賞の受賞対象になり、石井さんはこの賞を受賞されました。こちらの賞は「男女共同参画社会形成の推進あるいは女性文化研究の発展に寄与する研究を対象」とするものだそうですが、本作の内容は、当然ながら、この賞の対象となるに相応しいものです。しかし、それだけではありません。ある委員は本作について次のように評価しています。 「従来の専門職研究の枠を大きく超える力作。比較ジェンダー史・比較社会史研究の新境地を開いた。」 歴史学の立場からも、ジェンダー研究の見地からも、社会文化研究あるいは女性文化研究の場から見ても高く評価される本作は、分野の壁を越えた研究を目指すドイツ学会の差し上げる奨励賞の対象として最適であると言ってよいのではないでしょうか。 |
|
|
石井香江氏の受賞のあいさつ ただいまご紹介にあずかりました同志社大学の石井香江と申します。この度は、拙著をドイツ学会奨励賞にお選びいただきまして、誠にありがとうございました。ご推薦下さった方をはじめ、ご講評下さった選考委員の先生方に、この場を借りまして、深くお礼を申し上げたいと思います。幾つかの書評で頂きました貴重なご指摘、ご批判の数々を真摯に受け止め、今後の研究活動で取り組んでいく課題にしたいと存じます。 早速ですが、私の研究のバックボーンとなる学問分野は社会学です。現代社会の問題に対する関心が先にあり、その由来を探るために歴史的アプローチをとる姿勢を明確にしてきました。拙著もこうした研究スタイルから生まれていますので、理解が得られないのではないかと危惧していましたし、もっと工夫の余地があったことも強く自覚しております。ですので、受賞のご連絡を頂いた時は、正直なところ大変驚きました。社会学と歴史学の対話を、強引ながらも試みようと挑戦した点が、学際的研究として評価して頂いた理由ではないかと推察しています。 本書は、19世紀後半から20世紀初頭において、この時代を大きく動かした情報通信技術である電信・電話の誕生と発展のプロセスに注目し、それがドイツと日本において、技術を扱う労働力の配置、職場のジェンダー秩序に与えたインパクトについて比較検討しています。世界のグローバル化を牽引した電信・電話の、インフラとしての役割に注目する経営史・経済史的な研究に比べ、拙著のように電信・電話を扱う職場、そこで働く現業労働者・オペレーターに焦点を当てて、時代の特徴を描きだす社会史的・技術史的研究は、日本ではあまり見られませんでした。 ところで、本書の表紙の絵は、読者の方にとってインパクトが強いようで、関心を持ってくださる方が少なくありません。これは、民衆の日常を描いたドイツの画家ヴェルナー・ツェーメが、19世紀末のベルリンの電話局の様子を描いたものです。電話交換手といえば女性の職業の先駆けであり、女性たちが切り拓いた職業として知られていますが、歴史をたどれば男の仕事として出発しました。この絵は、技術革新を一つの契機として、電話交換手が男性から女性市民層の仕事に移り変わっていく瞬間をとらえた貴重な一枚といえます。 電話交換手が女の仕事であった事実についてはよく知られていますが、その理由や経緯について、必ずしも説得的な説明がなされてきたわけではありません。本書ではこのブラックボックスに迫るために、逓信省や各地の電信・電話局の公文書、社史、従業員が購読する機関誌や新聞に加え、職場のリアリティを描く回顧録や小説までを検討しました。また日本に関しては聞き取り調査も試みました。 本書の特徴は電話交換手が女の仕事になっていく過程を、電信技手が男の仕事になっていく過程と表裏一体のものとしてとらえ、関係史的に分析している点です。もう一つの特徴は、日独間の比較史であるという点です。電信・電話は欧米で開発され、ほぼ同時期に世界中に伝播し、世界の隅々を結びました。このため各国は、技術の使い方や担い手についての情報を共有し、互いに参照し合っていたのです。比較の視点は自ずと生まれ、ドイツと日本の間に多くの共通点を発見する一方で、技術革新の速度や「職場文化」の有無、その持続性という相違点も確認できました。本書では比較という方法を自己目的化するのではなく、日独の間に相違点を見出し、そこを可能な範囲で掘り下げるためのツールとして活用しました。ご批判はありましたが、ジェンダー秩序を日々生成する職場文化の存在は、一国史的な枠組みで研究していたのでは、気づきえなかったことと思います。 ただし、日本の職場文化に注目したがゆえに、歴史学では重要と思われるテーマ、例えば二度の世界大戦時の国内外での女性労働の実態を掘り下げることは、あえてしませんでした。電信・電話は重要な軍用技術でもありましたし、女性の戦争への動員というテーマとは切り離せません。こうした課題については、今後あらためて正面から向き合っていくつもりです、と決意表明をさせていただき、私からのご挨拶を終わらせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 |
  |
2017年度日本ドイツ学会奨励賞は該当作品なしでした。
2016年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
に授与されました。2017年6月4日、筑波大学東京キャンパス文京校舎において開催された日本ドイツ学会大会に際して授賞式が行われ、奨励賞選考委員会の村上公子委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会香川檀理事長から板橋氏代理の吉田書店吉田真也氏に賞状と副賞が手渡されました。 |
|
選考理由
2016年度日本ドイツ学会奨励賞は、 板橋拓己著『黒いヨーロッパ ドイツにおけるキリスト教保守派の に差し上げることとなりました。 ここで著者ならびに受賞作の概要をご紹介し、審査経過をご報告申し上げます。 板橋拓己さんは1978年栃木県生まれ。2001年北海道大学法学部卒業、08年同大学大学院法学研究科博士後期課程修了。法学博士の学位を取得されました。現在は成蹊大学法学部教授を務めておられます。 受賞作『黒いヨーロッパ』には、長い副題「ドイツにおけるキリスト教保守派の「西洋(アーベントラント)」主義、1925~1965年」がついていますが、この副題はそのまま、この作品の主題を示しています。『黒いヨーロッパ』の「黒」とは、キリスト教聖職者の纏う法服の色を指し、そこからキリスト教、とりわけキリスト教系の政党を暗示する表現としても用いられています。ドイツのニュースでは、Schwarz-RotとかSchwarz-Grünという言い方で、キリスト教民主・社会同盟と社会民主党の連立や、緑の党との連立を示すことがよくあるのは、ご存じのとおりです。 筆者は序章において「本書では…キリスト教系の政治勢力のなかでも、最も保守的で『反近代的』なグループを中心に20世紀におけるキリスト教系政治勢力とヨーロッパ統合の関係を考察する」と述べています。だからこその『黒いヨーロッパ』であり、その「最も保守的で『反近代的』なグループ」こそ、「『アーベントラント(Abendland:西洋)』というスローガンを掲げて、ある種のヨーロッパ統合を支持してきたキリスト教保守派の人びと、いわゆる『アーベントラント主義者』」であるわけです。 本書の内容について、一言付け加えるならば、筆者は第二次世界大戦後、ドイツ連邦共和国の「西側結合路線」を選択、推進した初代連邦共和国首相コンラート・アーデナウアーがアーベントラント運動に親和的な発言を繰り返していたことなどから、この運動が戦後のドイツの、そして統合ヨーロッパへと向かうヨーロッパの政治史に、少なからぬ影響を及ぼした可能性があることを指摘しています。 次に、奨励賞審査の経過をご報告申しあげます。今回審査対象となったのは4冊でした。 審査委員8人全員が4冊全てを読み、例年通り10点満点で評価したものを事務局で集計し、5月7日、早稲田大学において審査委員会を開催いたしました。出席の委員は6人でした。ここでまず、集計結果に従って、1冊を審査対象からはずし、3冊を授賞対象作として議論を行いました。実は、板橋作品は最初の集計では最高点ではなく、残りもう一点の作品と合計点では同点だったのですが、対象とする研究分野内での評価、ならびにテーマの学際性を考慮した結果、板橋作品を受賞作とすることで出席委員全体の合意が得られ、その後、欠席委員の合意も得て、板橋作品にドイツ学会奨励賞を差し上げることが決まりました。 審査経過からもお分かりいただけるとおり、板橋作品には歴史研究を専門とする委員から非常に高い評価が寄せられました。ある委員は「研究上の間隙をつくもので、新境地開拓の努力を多としたい。日本のドイツ研究に及ぼすインパクトはかなり大きい」との所見を示しています。それに対して、歴史研究の専門家ではない委員からは、「なかなか焦点を結ばず、データは増えても結局肩すかし的印象となってしまう」といった辛口の評価が多く示されました。 テーマが魅力的であることは全員が認めているところですので、ドイツ学会奨励賞審査委員会としては、板橋さんが今後も、刺激的なテーマに果敢に取り組まれ、門外漢にも分かり易い記述を身につけられることを願ってやみません。 |
|
2015年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
の二点 に授与されました。 2016年6月12日、早稲田大学において開催された日本ドイツ学会学術総会に際して授賞式が行われ、奨励賞選考委員会の村上公子委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会香川檀理事長から速水氏と吉田氏に賞状と副賞が手渡されました。 |
|
選考理由 2015年度日本ドイツ学会奨励賞は、2006年、2013年度に続く三度目になりますが、二作品に差し上げることとなりました。受賞作は、著者五十音順に、 速水淑子(はやみよしこ)さんの『トーマス・マンの政治思想 ― 失われた市民を求めて』創文社刊と 吉田寛(よしだひろし)さんの『絶対音楽の美学と分裂する<ドイツ> 十九世紀』青弓社刊 の二つです。 両作品の著者と作品の概要をご紹介し、審査の過程についてご報告申し上げます。 速水淑子さんは、東京大学大学院農学生命科学研究科修士課程修了後、慶應義塾大学法学研究科博士課程を修了、博士号を得られました。現在は慶應義塾大学法学部非常勤講師でいらっしゃいます。受賞作は、博士論文を大幅に修正、加筆したものである、とのことです。 受賞作『トーマス・マンの政治思想』は、著者によれば「トーマス・マンの政治思想を、市民性とのかかわりを軸に明らかにすること」を目的とし、「マンの思想を『歴史的に与えられた社会的思想的原状況』に対する応答として読み解く」試みです。このように申し上げると、既視感を持たれる方もおいでかと存じますが、速水作品の特徴は、その分析の広さ、深さ、そして緻密さと周到さにあります。 審査委員の一人は「市民と市民性という鍵概念を…同時代の関連分野に目配りをしながら、平明な文章で掘り下げている点に感銘を受けた」と述べ、別の一人は「マンの多様な発言をこれほど明解かつ網羅的にまとめた本を初めて見る思いがする」と評価しているところからも、速水さんの分析の秀逸さがお分かりいただけるでしょう。 吉田寛さんは東京大学大学院人文社会系研究科(美学芸術学)博士課程修了ののち、学位申請論文『近代ドイツのナショナル・アイデンティティと音楽―《音楽の国ドイツ》の表象をめぐる思想史的考察』によって博士号を取得。同研究科助教、立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授を経て、現在は同教授でいらっしゃいます。受賞作はこの博士論文を元にして出版・発表された一連の(四冊の)著作の最終作であり、博士論文の第5章に加筆・修正を加えたものです。 受賞作『絶対音楽の美学と分裂する<ドイツ>』は、少々乱暴にまとめますと、19世紀に起こった音楽における「ドイツ的なるもの」の評価の変遷と、政治理念としての<ドイツ>の変遷と分裂を重ね合わせてそのあり様を記述したもの、と言えるでしょう。蛇足ですが、吉田さんは本作品で2015年度サントリー学芸賞を受賞されています。 双方の研究分野が近いこともあり、できれば二作品同時受賞は避けたいと、様々な側面から議論しましたが、どちらか一方を選ぶ決定的な論拠を提示することができず、結局、分野は近接であっても、双方の研究スタイルはまったく対照的で、分野のクロスオーバーだけでなく、研究手法の多様性を認めるという意味で、二作品に奨励賞を差し上げてもよいのではないか、という結論に至った次第です。 |
   |
|
速水淑子氏の受賞のあいさつ このたびは、栄誉ある賞を与えられ、たいへん光栄に感じております。講評をいただいた先生方、そして、執筆に際し指導を受けた慶應法学部政治思想専攻の先生方に、改めてお礼を申し上げたく存じます。 本研究は、1900年代から第二次世界大戦後まで、約半世紀にわたるトーマス・マンの「政治思想」の変遷を、小説、論説、書簡、日記の分析を通じて論じたものです。政治思想家としてのマンに関心を持ったのは、学部二年生の語学の授業で読んだ、「芸術家と社会」という小論がきっかけでした。その小論の終わりのほうで、マンは、「芸術家が政治的に道徳を説くということに、なにか滑稽なところがあるのは否定できない(Unleugbar hat ja das politische Moralisieren eines Künstlers etwas
Komisches)」と述べていました。亡命を余儀なくされ、息子や友人を失いながら、ファシズム、ナチズムとの闘いを訴えてきたマンが、最晩年の1952年に、自分の政治活動を振り返って、「滑稽」なものであったと総括しているのは、それだけで異様なことですが、同時にまた、この言葉を通じて「政治」というものの輪郭が、「芸術」の側から思いがけず照らし出されたような、そういう強い印象を受けました。 それから文献を読み進めまして、マンの思想世界においては、彼が晩年に「存在への共感」と呼んだような精神態度、危険で有害なものにさえも向けられる無制限の共感が、芸術家に不可欠のものと考えられており、そして「政治」はこの共感に排除と暴力の契機を以て制限を加えるものとして捉えられていたのだと、考えるようになりました。こうした「政治的なもの」に対する警戒の一方で、マンには、それとは異なる「社会的なもの」への期待がありました。それは、個人が「無制限の共感」を共同性と照らし合わせて自己規制し、それによって個人の内的涵養と社会的連帯が相即的に発展していくという教養のプロセスを指しているのですが、ワイマール期以降、この理想が、宇宙論や物語論の構築を含めた、市民的人文主義の再解釈という壮大なプロジェクトとなって表れたことも見えてきました。 研究では、このプロジェクトの背景にあるマンの歴史あるいは現状認識を、同時代のコンテクストに位置づけ、批判的に相対化することにも重点をおきました。ただしこれについては課題が多く残り、例えば「有機体としてのドイツ」や「東西の中間にあるドイツ」といったマンの言説について、当時の言論状況と照らし合わせて、より批判的に検討するべきであったと、すでに批判をいただいているところでもあります。本日の受賞をきっかけに、各分野の専門家の方々から、さらなるご批判を頂くことができれば、そしてそれを、ドイツ人文主義と政治の関係を振り返るという長期的な研究目標に活かすことができれば、と願っております。本日はありがとうございました。 |
  |
|
吉田 寛 氏の受賞のあいさつ 立命館大学の吉田寛と申します。 この度は、拙著『絶対音楽の美学と分裂する〈ドイツ〉』を、日本ドイツ学会奨励賞にお選びいただきまして、誠にありがとうございます。日本のドイツ研究をリードする本学会の先生方に、拙著をお読みいただき、またご関心をもっていただいたことは、身に余る光栄です。 実は私は、日本ドイツ学会へは今回で二度目の参加となります。前回の参加は、2011年6月に新潟で開かれました第27回総会でした。そこでのシンポジウム「音楽の国ドイツ?──音楽と社会」にお招きいただき、研究発表をし、その後『ドイツ研究』に論文も掲載していただきました。その時点では、ちょうど本書を第三巻とするシリーズの、第一巻を書いている途中でした。このシリーズの副題は「〈音楽の国ドイツ〉の系譜学」といいますが、その副題を考えている際、その学会シンポジウムの題名と完全にかぶってしまうが大丈夫だろうか、真似したと思われたらちょっと悔しいなあと、気にしたことを今も覚えております。ともかく、そのシンポジウムや論文掲載の過程で、本学会の皆様から大きな刺激と励ましをいただいたことが、拙著として結実しました。今あらためて感謝の意を表します。 私はドイツ語やドイツ文化の専門家ではございません。現代音楽の研究からスタートし、現在は感性とメディアを研究しています。芸術からもドイツからも離れてしまっています。ドイツ語は資料を読むために使うくらいで、ほとんど話せません。ドイツへは調査には行きましたが、留学などはしておりません。ドイツで学会に出るときも、英語で話しています。しかし、ドイツとその程度の関わりしかない私でも、音楽とナショナル・アイデンティティの研究をするためには、どうしてもドイツのことをやらざるをえなかった。それくらい、音楽という芸術とドイツという場所は、密接に結び付いている、ということです。そのことは拙著によってわずかでも明らかにできただろうと自負しています。そして、そのような私が、音楽を研究するなかで、ここまで深くドイツの問題に立ち入ることができたのは、大学の学部時代によいドイツ語の先生に、また大学院時代に優れたドイツ研究者に、たくさん巡り会えたためです。図書館にドイツ語の文献が豊富にあったためです。それはとりもなおさず、日本におけるドイツ研究の伝統と成熟のおかげだと思っています。わざわざ留学などしなくとも、日本にはドイツ研究のための十分な環境がある、ということです。それは素晴らしいことであり、またこれからも長く維持されるべきことだと思います。その意味でも、日本のドイツ研究を日々支えておられる本学会の皆様には、深く敬意を表します。 ドイツの文化や歴史の専門家が、拙著をどうお読みになったのかを知るのは、正直言ってたいへん怖いことです。音楽研究や思想研究の側から、精一杯のアプローチはしてみましたが、ドイツ史に関する私の理解や論述は、通り一遍、もしくは過度に図式的であったかもしれません。誤りもあるかもしれません。また拙著の後半の中心的視座となる、ドイツの南北問題、ドイツとオーストリアの関係についても、新しい研究が色々と出ていることが気にかかりなりながら、十分に扱いきれませんでした。この書で扱った問いは、十九世紀で完結するどころか、二十世紀を経て現代へ、そして今日へとつながっているものですので、いずれまた機会をあらためてじっくり調べ、考えてみたいと思っています。 本日はありがとうございました。日本ドイツ学会のますますのご発展を祈念して、私からのご挨拶の結びとさせていただきます。 |
  |
|
2014年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、 北村 厚 氏(東京成徳大学高等学校 専任講師)の に授与されました。 2015年6月20日、東京大学において開催された日本ドイツ学会学術大会に際して授賞式が行われ、奨励賞選考委員会の村上公子委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会姫岡とし子理事長から北村厚氏に賞状と副賞が手渡されました。 |
|
選考理由 平成14年度日本ドイツ学会奨励賞は、北村厚さんの『ヴァイマル共和国のヨーロッパ統合構想』に差し上げることとなりました。奨励賞審査委員会を代表して、受賞者ならびに受賞作品をご紹介すると同時に、審査経過をご報告申し上げます。 北村さんは、1975年福岡市生まれ、2004年に九州大学大学院法学府博士課程を単位取得退学され、2007年に同大学で法学博士号を取得されました。現在は、東京成徳大学高等学校専任講師として、世界史を担当していらっしゃいます。 受賞作『ヴァイマル共和国のヨーロッパ統合構想』は、九州大学に提出された博士論文を元に、7年の歳月をかけて大幅に加筆、修正されたものだそうです。 本書のテーマは、題名からも明らかなとおり、第一次世界大戦後のヨーロッパ没落という時代の流れの中で、ヴァイマル共和国ドイツにおいて希求されたヨーロッパ統合の理念と政策を解明することです。もちろん、大戦間のヨーロッパで、ヨーロッパ統合理念を追求したのはドイツに限りません。日本でもよく知られているクーデンホーフ=カレルギー伯のパン・ヨーロッパ論を初めとして、各国でそれぞれの思惑を踏まえたヨーロッパ統合論が唱えられていたようです。 北村さんのご著書は、これら複数のヨーロッパ統合論を紹介するとともに、それらを踏まえたうえでのヴァイマル期のドイツにおける独自のヨーロッパ統合理念と、それを実現させるための政策の進展、並びにそれが最終的に挫折に終わるまでの経緯を、史料に基づき、丹念に論じたものです。 次に、簡単に、審査の経過についてご報告申し上げます。 今回、奨励賞の審査対象となったのは、北村さんのご著書ともう一冊の、計二点でした。まず、審査委員全員がこの二作品を読み、それぞれ10点満点で評点をつけ、その上で、5月10日に奨励賞審査委員会を開催し、出席した委員の間で協議を行いました。今回の審査では、比較的短時間の話し合いで、北村作品に奨励賞を差し上げることが決まりました。大戦間のヨーロッパ統合論について、ドイツ史の立場から説得的に論じた点が高く評価されたものです。ただし、評者によっては、「重要な大局的テーゼと細部の事実関係の議論があまり整理されずに並べられて記述される箇所が多い」ため、わかりにくい、という批判もあったことを付け加えておきます。 日本ドイツ学会奨励賞審査委員会としては、北村さんが、これまでのご研究の成果を踏まえ、今後さらに共時的また通時的にも研究の視野を広げて、さらに充実した業績を重ねられることを心から期待いたします。 |
 |
|
北村 厚 氏の受賞のあいさつ 東京成徳大学高等学校の北村厚と申します。このたびはドイツ学会奨励賞を受賞するという、身に余る栄誉を賜りまして、感謝申し上げます。 拙著はドイツ近現代史における大きなテーマである「中欧」 私の研究は、何か生涯をかけて追究しなければならないような使命感を持って最初から取り組んだものではありません。自分が面白いと思ったテーマを一つ一つ積み重ねていった結果、その歩んできた道のりを振り返ってみて、実は全体としてやりたかったのはこのテーマだったのだと、後から理解したというものです。そのため、この研究が現代社会にとって何の役に立つのかとか、専門外の読み手を引き付けるエネルギーといったものはないかもしれません。まずは西洋史が面白いということで歴史学に取り組み、いつの間にか立派な本を刊行するまでになったわけです。 ちょっと後半拙著の内容からずれてしまいましたが、最後に、これまでご指導いただいた先生方、そしてこの素晴らしい賞を授けていただいた日本ドイツ学会の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。 |
|
2013年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
の二点 に授与されました。 2014年6月7日、武蔵大学において開催された日本ドイツ学会学術総会に際して授賞式が行われ、奨励賞選考委員会の村上公子委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会姫岡とし子理事長から青木氏と福岡氏に賞状と副賞が手渡されました。 |
|
選考理由 2013年度日本ドイツ学会奨励賞は青木 お二人の受賞作のご紹介は後ほど行うとして、先に、今年度の審査経過をご報告申し上げます。例年通り、2013年中に出版された書物のうち、学会奨励賞にふさわしいと思われる候補作を推薦してくださるよう、学会員の方々にお願いし、その結果、四作品が審査対象とすべき候補作となりました。審査委員はこの四作品全てを読み、それぞれについて10点満点で採点し、コメントを添えて提出いたしました。最終的な審査委員会は5月5日、早稲田大学で行いましたが、その際、提出された点数ならびにコメント全てを奨励賞事務局の西山暁義さんが集計した資料が用意され、審査はその資料に基づいて、当日出席可能であった審査員によって行われました。 四作品のうち二つは、それぞれ理由は異なりますが、今年度の受賞作とするにはふさわしくないということで、出席委員の合意が得られました。残ったのが、青木さんと福岡さんの作品でした。この段階で、委員の間の議論は、両者同時受賞にすべきか否かという点に集約されたと言ってよいと思います。できることならば、二作品の同時受賞は避けたいところだったのですが、しかし、両者は平均得点も同一で、最高点をつけた委員の数も同じという、ドイツで言う”patt”な状況になっており、局面を大きく動かすような議論も出ませんでした。出席委員間でかなり慎重に話し合いを重ねたのですが、結局、この二作品のうち、どちらを選んだとしても、もう一方を選ばなかったことを後悔することになるだろうという懸念を捨てることができなかったのです。 当日出席していた審査委員の見解として、①青木さんと福岡さんの作品は、全く分野が異なる。②いずれの作品も、各々のあり方で、学際性、学術性、そして社会へのコミットメントを重視するドイツ学会の奨励賞受賞にふさわしい特質を示している。ことから、両作品の同時受賞を容認すべきである、という結論を出し、当日欠席であった委員の了承をまって、それを最終結果といたしました。 ここで、ごく簡単に、二つの作品をご紹介いたします。どちらも、題名がほぼそのまま内容を示していると言ってよいのですが、青木さんの『ドイツにおける原子力施設反対運動の展開 - 環境指向型社会へのイニシアティヴ』は、ドイツの反原発(だけではないので、青木さんは原子力施設と言っていらっしゃるわけですが)運動の発生から現在までを、フィールドでの具体的かつミクロな調査と、環境社会学のマクロな学問的枠組みを用いた分析の双方を駆使して、バランスよく論述した作品です。審査委員からは、この作品の持つメッセージ性に心を揺さぶられた、という感想と、そこに懸念を持つという声の双方が聞かれたことを申し添えます。 福岡さんの『プロイセン東アジア遠征と幕末外交』は、オイレンブルク使節団という名で呼ばれることも多い「『プロイセン東アジア遠征Preußische Expedition nach Ostasien』の派遣をめぐる国際的背景と日本=プロイセン修好通商条約の成立過程を、幕末…の日本を取り巻き、また舞台とした外交史・国際関係史の文脈の中に位置づけつつ、詳細に明らかにする…」作品です。確かに、この著書の内容はそれ以下でも以上でもないのですが、その「詳細」緻密さの極みと言うべき実証研究の厚みと、複数の言語による資料を丁寧に読み込むことで、固定化された歴史記述を説得的に脱構築する解釈の大胆さには圧倒されます。とまあ、「世界史的アプローチの顕現」に興奮する審査委員と、学際性の点で懸念があるとする審査委員双方の声が、この作品についても聞かれました。 日本ドイツ学会奨励賞審査委員会としては、お二人が日本ドイツ学会という、このような学会からの賞を受けられたことを新たな契機として、それぞれのご研究を深めるだけでなく、広げていらっしゃることを心からお祈りいたします。 |
|
|
青木聡子氏の受賞のあいさつ 名古屋大学の青木聡子と申します。このたび日本ドイツ学会奨励賞をいただくこととなり、大変光栄に思っております。この場を借りまして、拙著を推薦して下さいました方、学生時代の指導教員の先生方や調査先で出会った方々をはじめとしてこれまでの研究生活でお世話になってきたすべての方々に深く御礼申し上げます。 個人的な話で恐縮ですが、私は宮城県の出身です。そして小学校低学年のときにチェルノブイリ原発事故が起き、子ども心に原発を怖いと思いました。それと同時に、自分の住んでいる県にも女川原発という原発があることを知り、とても不安になったことを今でも覚えています。なぜ原発なんて危険なものを使っているのか、しかもよりによってなぜそれが自分の地元にあるのか。なぜ大人たちは原発を止めてくれないのか。振り返ってみれば、この当時の子どもながらの不安や不満が現在の研究の出発点になっているように思います。 東日本大震災の際には、女川原発はなんとか事故をまぬがれました。しかし、同じ東北の地、福島県で福島第一原発が大事故を起こしました。結果的にそれがドイツを脱原発へと向かわせる決定打になったことは、私にとって大変皮肉な事態で、本当に無念でなりません。 その意味で、2011年のドイツのエネルギー転換は私にとってみれば大変不本意と言わざるを得ないわけですが、とかく2011年のみが強調されることも私にとって大変違和感のあることです。2011年がドイツのエネルギー政策の重大な転換点であったことは間違いありませんが、福島第一原発事故がこれほどまで迅速かつ決定的にドイツの脱原発へと直結した背景には、40年以上にわたって着々と敷き置かれてきた、脱原発に向かうレールの存在を指摘できます。ドイツの脱原発は「2011年」がすべてではない、福島第一原発事故が「引き金」になったことは確かだが、それは遅かれ早かれ何らかのかたちでもたらされ得た「引き金」であった、というのが私のスタンスであり、拙著では脱原発に至るレールがいかにして敷き置かれてきたのかを明らかにしようとしています。 その際に、原子力施設に抗う人々にとりわけ焦点を当てたのは、子どもの頃の感情と関連付ければ、「原発を阻止してくれる大人たち」に魅力を感じたからかもしれません。人々は何を思ってどのように運動に身を投じ、彼/彼女らのその身を投じるという行為はどのようなかたちで報われるのだろうか。これが私の一貫した問題関心で、拙著はこの問題関心にできるかぎり応えようとしたものです。そのすべてに応えられたわけではありませんが、私なりに人々の闘いっぷりや抗いっぷりを描き切ることはできたと思っています。そしてそこから明らかになったのは、運動を目的達成のための手段としてとらえるのではなく、運動それ自体を目的とするような運動観の存在であり、極端な言い換えをすれば、たとえ原子力施設を阻止できなくともそれに抗ったという事実が残るということ、それを意識しながら運動に身を投じる人々の姿でした。こうした人々の抗いの積み重ねが、結果として2000年の脱原発合意へと結実し、最終的には2011年のエネルギー転換へとつながったわけですが、「運動と政策転換のあいだ」を十分に描き切ったとはいえず、私の研究課題として残っております。加えて、脱原発後のドイツ社会、とりわけ原発立地地域に生きる人々が、自らが直面することとなった困難な状況と向き合いそれを克服していくプロセスを見届け検証するという新たな課題も浮上してきました。今後はこれらの課題に取り組みながら研究を進め、そこから得られたものを日本社会に還元できればと思っています。 本日はありがとうございました。 |
|
|
福岡万里子氏の受賞のあいさつ このたびは、栄誉ある賞を賜りまして、誠にありがとうございます。 拙著は、1860年に来日したプロイセン東アジア遠征という素材を通して、幕末の動乱・変革期の日本が置かれた外交史的状況、東アジア国際関係史の中で置かれた立ち位置について、考察を試みたものです。遠征の結果結ばれた1861年の日本プロイセン修好通商条約は、当時の日本の入り組んだ不安定な内政外交状況の中でなぜ締結され得たのか。と同時に本来は条約に参加するはずだったプロイセン以外の一連のドイツ諸国が条約から外されたことは、同時代の東アジアの中ではどのような意味を持ったのか、またそれは、当時の日本外交の性質についてどのようなインプリケーションを持つのか。遠征に関わる史料の中に見出される極めて多様な情報やアクターたち、それはプロイセンや日本のみならず、オランダやハンザ諸都市、シャムや中国、アメリカやイギリスその他、背景や出自は多岐にわたるのですが、それら/彼らは、どのような国際的なコンテクストの中で、ひしめき躍動していたのか。拙著は、このような問題を、諸々の史料や文献と格闘しながら考え、読み解こうとしたものです。 ドイツ語を使い、日本史を学問的フィールドとして研究成果を発表しようとする私のアプローチは、始めた当初は類似の例があまりなく、いささか心細い思いでした。そうした中で、プロイセン東アジア遠征という魅力ある素材の存在を教えて下さったドイツ研究分野の指導教官・臼井隆一郎先生、この素材を幕末外交史研究で生かしていく道筋を照らして下さった日本史分野の指導教官・三谷博先生をはじめ、様々な指導者の方々のお力添えを頂きつつ、最初の成果をまとめることができました。今回、日本のドイツ研究を牽引する日本ドイツ学会から奨励賞を給わる栄誉に恵まれ、大変有り難く思いますと同時に、勇気づけられております。本賞は「ドイツ語圏に関する将来性に富む優れた研究業績を顕彰し、ドイツ語圏に関する学際的学術研究の発展に資することを目的」として設けられた賞と伺いました。ドイツ語圏に関わる研究のひとつの可能性あるあり方として、このようなアプローチを認めていただけたことと思い、今後の研究の励みとしていく所存です。現在、ドイツ語、ないしその他の西洋言語を使った日本、東アジアに関する研究は、携わる人がまだかなり少ない状況です。しかしそれだけに、開拓されていない未知の可能性が豊富に詰まっている領域であると言えます。今後、私の試みがひとつのささやかな先例となり、同様のアプローチをとってこの分野の探検に乗り出そうとする方が少しでも増えれば、大変嬉しいことと思っております。 最後に改めまして、今回賜りましたご評価とご激励に、心からの御礼を申し上げまして、結びとさせていただきます。 |
|
|
2012年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
に授与されました。 2013年6月22日、お茶の水女子大学において開催された日本ドイツ学会学術総会に際して授賞式が行われ、奨励賞選考委員会の村上公子委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会姫岡とし子理事長から村上宏昭氏に賞状と副賞が手渡されました。 |
|
選考理由 本年度の日本ドイツ学会奨励賞の受賞作品は、村上宏昭著『世代の歴史社会学 – 近代ドイツの教養・福祉・戦争』2012年昭和堂刊に決定いたしました。 著者の村上宏昭さんは、1977年生まれ、関西大学大学院文学研究科史学専攻を修了して博士号を取得、日本学術振興会特別研究員を経て、現在は、助教として、筑波大学人文社会系に奉職しておられます。 日本ドイツ学会奨励賞審査委員会における、審査の経過を簡単にご説明いたします。2012年に出版された書籍のうち、奨励賞の審査対象とすべき作品の推薦を学会員の皆様にお願いしましたが、その結果、締め切りまでに4作品が推薦されました。 奨励賞審査委員全員が全4作品を読んだ上、それぞれを10点満点で評価し、コメントを付けたものを、事務局が集計いたしました。この集計を踏まえ、2013年5月5日、審査委員会を開催し、慎重、そしてかなり時間をかけた議論の結果、村上宏昭さんの作品に奨励賞を差し上げることが決まりました。 議論に時間がかかったのは、次点となった作品も非常に優れた論考で、そちらの作品をより強く推す審査員も、一人ならずあったからです。しかし、最終的には、学際性を重んずるドイツ学会の奨励賞として、よりふさわしい作品である、という点が重視され、村上宏昭さんの作品が選ばれました。 ここで簡単に、受賞作『世代の歴史社会学 – 近代ドイツの教養・福祉・戦争』の内容をご紹介いたします。題名にあるとおり、この著作の主題は世代論です。ご存じのとおり、ドイツでは、近代から現代にかけて、青年神話、青年主義など、様々な世代論が登場しました。本書は、これらの世代論を「ライフステージ」と「コーホート」を鍵概念として、また教養理念や優生学、社会国家などの問題と結びつけて整理・分析したものである、とまとめることができるでしょう。著者自身は、序章で、「本書の課題は…『社会的事実』としての世代形象についてささやかな歴史的考察を行うこと…もっといえば…アイデンティティとしての世代意識にしろ、あるいは研究上の分析ツールとしての世代概念にしろ、世代をめぐる考え方が20世紀に入って大きな変化を経験したという仮定のもと、その検証を行うことが本書の目的」であると述べています。 奨励賞審査委員からは、この「世代」を歴史研究における重要な分析概念として正面から取り上げ、これまでの世代理論を整理し、世代概念が根底的転換に至った背景を科学史的に考察し、更に20世紀の世代概念成立の過程を論述するという、本書の壮大な試みと、その学問的到達度が高く評価されました。 ただ、意図の壮大さゆえか、理論構成が必ずしも平明とは言えない、あるいは、「世代」概念を歴史研究においてどのように使用すべきかについて、著者自身判断に揺れがあるのではないか、とか、また著者が本書の「中心課題」としている世代概念イメージの「ライフステージ」から「コーホート」への転換の軌跡を再構成する、という意図が成就されているようには思えない、という批判的なコメントもあったことを付け加えておきます。 ともあれ、日本ドイツ学会奨励賞審査委員会としては、村上宏昭さんに、奨励賞受賞のお祝いを申し上げるとともに、今後とも精力的に研究を進められ、何よりも、ドイツ史、あるいは歴史学という枠を越えた、領域横断的なお仕事を発表し続けて下さいますよう、お祈り申し上げます。 |
|
村上宏昭氏の受賞のあいさつ 筑波大学の村上宏昭と申します。このたびは、栄誉ある日本ドイツ学会奨励賞をいただくことになり、望外の喜びに存じます。まずは、この場を借りて拙著を推薦していただいた方、ならびにこれまでの研究生活でお世話になった関係者の方々に深く御礼申し上げます。 さて、拙著の中心的なテーマはタイトルにもございますように「世代」です。ご存じのとおり、この世代というテーマはつい数年前まで日本社会でも一世を風靡した観がありました。今はその熱も少し冷めているようですが、この本の基となった論文を執筆していた時期は、ちょうど「ロストジェネレーション」という非常にありがたくない名前を付けられた年齢集団(コーホート)が、新自由主義批判の渦巻く中で脚光を浴びていました。そのせいか、当時は猫も杓子も世代論という、悪く言えば「ウケ狙い」、良く言っても「一面的」と言わざるをえないような議論がいたるところで噴出し、その反動で世代という切り口そのものに対する懐疑のまなざし、世代論の持つ胡散臭さが、これまでにないほど意識された時期でもあったと思います。 私の短い研究生活から実感として感じるのは、こうした社会的な流行なり風潮なりは、学術研究にとってきわめて両義的なものであるということです。つまり、一方では自分が従事する研究テーマに関して、言葉や理屈をいちいち並べ立てなくても直にその意義を理解してもらえるというメリットはあります。しかし他方では、自分自身もそうした安直な理解に囚われてしまい、距離を置いた冷静な分析がしばしば困難になるというデメリットもあります。いうまでもなく、後者は学問的な考察を進めるにあたってほとんど致命的とも言えるデメリットであり、流行が過ぎ去るとともにその寿命も尽きてしまう、息の短い泡沫研究しかできなくなる恐れが多分にあります。 振り返ってみれば、私自身もしばらくこうした陥穽に陥っていたことは否めませんし、それだけに世代論の持つ学問的意義に対して懐疑的な声が上がるたびに、ある種のもどかしさを感じていたことも事実です。ただ急いで言い添えておけば、そのような懐疑や批判があったからこそ、私もまた徐々にではあれ世代論を相対化して考えるようになり、そうした懐疑の念を起こさせる歴史的理由、つまり「なぜ世代はこれほどまでに胡散臭い概念になったのか」という、新たな問題意識へと導かれていったと言えます。その意味で、拙著がこの学会奨励賞に値する意義を持つとすれば、それはまさしく私の視点を流行の渦中から引き離してくれた真摯な批判や懐疑の声、それに数々のお叱りの言葉に負っています。それゆえ本日の栄誉は私個人の力量というより、私の周囲の方々によるお力添えの賜物であると認識しております。 本日はどうもありがとうございました。 |
|
|
2011年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
に授与されました。 2012年7月7日、東京大学大学院数理科学研究科大講義室において開催された日本ドイツ学会学術総会に際して授賞式が行われ、奨励賞選考委員会の村上公子委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会姫岡とし子理事長から小原淳氏に賞状と副賞が手渡されました。 |
|
選考理由 2011年度のドイツ学会奨励賞受賞作は、小原淳著『フォルクと帝国創設 – 19世紀ドイツにおけるトゥルネン運動の史的考察』彩流社刊、に決定いたしました。ここで、選考委員会を代表して、受賞者小原淳さんの略歴をご紹介申し上げるとともに、選考の経過を簡単にご説明いたします。 小原さんは1975年生まれ、2006年に早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程を修了され、2008年、学位請求論文「近代ドイツにおける<市民性 Bürgerlichkeit>の変容 – 1840年代〜1860年代のドイツ・トゥルネン運動」によって早稲田大学から博士号を取得、現在は和歌山大学教育学部准教授として教鞭を執っておられます。言わずもがなかもしれませんが、今回の受賞作は、博士論文に加筆修正の上、出版されたものです。 今回、ドイツ学会奨励賞選考委員会では、まず、委員から推薦された三冊の候補作品を12名の選考委員全員が読みました。次に、三作品それぞれを十点満点で採点し、各々の作品に対する所見を付けて提出、事務局でそれを集計し、資料にまとめました。その上で5月6日選考会議を開催、資料に基づき、出席可能だった委員間で慎重、入念な議論と検討を重ねた結果、小原氏の作品が、学術的な質の高さに加え、とりわけ狭義の19世紀ドイツ史の枠を越えて、近代ジェンダー史や西洋教育史、文学、民俗学、さらには視覚文化研究に及ぶ、広範な研究分野への広がりの可能性を持つ内容であることから、学際性を標榜するドイツ学会の奨励賞にふさわしい、という結論に至りました。 本書は、その副題にあるとおり、19世紀初めにドイツの思想家にして教育者、フリードリヒ・ルートヴィヒ・ヤーンが創始した「トゥルネン」を、ジョージ・モッセのいう「大衆の国民化」に大きく寄与した運動と捉え、「トゥルネン運動がその成立以来一貫してフォルクの運動であることを自任し、フォルクについての理念と実践の交錯する場であり続けた」がゆえに「フォルクの歴史的内実とその変化を考える」ための格好の材料として、このトゥルネン運動を考察、分析するものです。 周知のとおり、フォルクという言葉の意味する内容は大変多重的ですが、筆者はラインハート・コゼレクに従ってこれを「内/外」と「上/下」という二つの軸に沿って、整理できるものと捉えています。 筆者によれば、発生から「帝国」創設期までの「トゥルネン運動」は、時期ごとに様相を変えつつ「フォルク」概念がこのコゼレクの「内/外」と「上/下」の二つの軸に対応する形で形成されていく実態を、見事に反映している、のだそうです。 本書を読む者は、詳細な実証的データに裏付けられた筆者の論述によって、「フォルクについての理念と実践の交錯する場」であり続けたトゥルネン運動の実態を目の当たりにすると同時に、その運動の内外で、徐々に立ち上がってくる「フォルク」なるものの存在を、そのありようの複雑さと共に、感じ取ることが出来るでしょう。 オーソドックスな歴史研究者としての筆者の力量には疑問の余地はありません。その確認の上で、歴史学会ではない、ドイツ学会の奨励賞選考委員から寄せられた、いわば、将来の氏の研究に対する期待とも言うべき指摘の何点かに、敢えて触れさせていただきます。 まず、本書の考察対象が少し限定的に過ぎるのではないか、という複数の指摘がありました。一つは、考察の直接対象となっているトゥルネン運動そのものについて、今少し後の、独仏戦争の時期まで考察する、あるいは、もう少し個々のトゥルナーの内面に踏み込んだ考察が欲しかった、という指摘です。 他の何人かの委員からは、フォルク形成の様相を検証する場として、トゥルネン運動以外の運動にもう少し言及した方が、考察に深みがでたのではないか、という指摘がありました。 しかし、ドイツ学会奨励賞選考委員会として、より重要と思われるのは、次の点です。既に選考経過説明の中で触れましたが、本書を推す選考委員のコメントには、本書の記述が19世紀ドイツの歴史研究を越えて、他領域の研究にとっても有意義である、という内容のものがいくつもありました。その場合、そこで言う「他領域」は、コメントを書いた選考委員本人の主たる研究領域であることが殆どでした。 これは、本書の持つ学際的意味の大きさを示す事実ですが、ただ、一つ気がかりなのは、そのコメントに必ずと言ってよいほど「筆者はあまり意識していないが」という留保がついていたことです。 選考委員会としては、小原氏が本書に至る研究の過程で蓄積されてきた、非常に豊かで多様性に富む学問的財産を、狭義の19世紀ドイツの歴史研究以外の視点から見た際の可能性にも目を閉ざすことなく、より豊かな研究を続けられることを願って已みません。 |
|
|
小原 淳氏の受賞のあいさつ 和歌山大学の小原でございます。この度は拙著『フォルクと帝国創設―19世紀ドイツにおけるトゥルネン運動の史的考察』に名誉ある賞をいただき、大変光栄に感じております。 これまでにこのような立派な賞を受けた経験もありませんし、「脱原発」がシンポジウムのテーマである今日のこの場で、体操やら愛国主義やらに夢中になっていた19世紀のドイツ人を対象にした研究について何をお話すればよいのか、正直見当がつきません。しかし、初めて日本ドイツ学会に参加させていただき、先ほどまでシンポジウムでの討議を拝聴したことで、賞に加えてもう一つ、今後の研究に励みをいただいたような気がしております。 こう申しますのは、拙著の執筆の最中に昨年の大震災が起き、そのような時に遠い異国、遠い時代の瑣末なあれこれを云々するのに何の意味があるのか、歴史学が眼前の惨事にいかに立ち向かうことができるのかを、大学の卒業論文でトゥルネン運動を研究テーマに選択して以来、初めてと言っていいほど切実に考えさせられたという経緯があるからです。昨夏に拙著を上梓した後も、この問いに自分なりの答えが得られたわけではなく、暗澹とした諦念を払拭しきれないままにいるのですが、専門家と一般の方の垣根を越えた今日の熱心な議論の応酬に耳を傾け、歴史研究はあるいは何らかの社会的有用性を持ち得るのかもしれない、少なくともその可能性を信じながら拙い研究を続けなければならないという思いを強くした次第です。 最後になりますが、拙著においては自制したことですが、常に私を支え続けてくれている家族への感謝をこの場をお借りして表現することをお許しいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。 |
|
|
2010年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
に授与されました。 2011年6月25日、朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターにおいて開催された日本ドイツ学会学術総会に際して授賞式が行われ、奨励賞選考委員会の石田勇治委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会姫岡とし子理事長から中村綾乃氏に賞状と副賞が手渡されました。 |
|
選考理由 ドイツ学会奨励賞選考委員会は、会員から推薦のあった三つの作品を候補作品として審査を行い、慎重かつ公正な審議の結果、中村綾乃氏の著書『東京のハーケンクロイツ-東アジアに生きたドイツ人の軌跡』(白水社、2010年刊)を2010年度奨励賞受賞作品とすることで一致しました。以下、簡単ですが、中村氏をご紹介し、あわせて選考理由についてご説明させていただきます。 |
|
|
中村綾乃氏の受賞のあいさつ このような賞をいただけることは、私のささやかな研究キャリアにおいて大変光栄なことです。これまで惜しみない助力を注いで下さったすべての方々に、この場を借りてお礼を申し上げます。 |
|
2009年度日本ドイツ学会奨励賞は授賞取り消しとなりました。 →詳細について
2008年度日本ドイツ学会奨励賞は該当作品なしでした。
|
2007年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
に授与されました。 2008年6月21日、筑波大学において開催された日本ドイツ学会学術総会に際して授賞式が行われ、奨励賞選考委員会の石田勇治委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会広渡清吾理事長から今野元氏に賞状と副賞が手渡されました。 |
|
選考理由 今野元氏は、これまで一貫してドイツ近現代史、とくに帝政期から第一次世界大戦を経てヴァイマル共和国にいたる時期を対象に、同時代の思想家マックス・ヴェーバーに焦点をあてた優れた論考を発表してきた。 今回の受賞作『マックス・ヴェーバー』(東京大学出版会)は、5年前に刊行された著書『マックス・ヴェーバーとポーランド問題』(同)で示されたヴェーバーの東方観に関する成果を踏まえ、ヴェーバーが明確な西欧近代化論者であると同時に、強いナショナリストであったという事実を、様々なエピソードを織り交ぜながら、説得的に描いた作品である。 最良の歴史書は人物研究であるともいわれるが、本書はヴェーバーの人物像をありのままに、―これを一方的に断罪することも、礼賛することもなく―、そして、ヴェーバーが直接向きあった同時代の具体的な政治、社会的文脈にも分析のメスをいれながら、活写している。その意味で、本書は伝記の形態をとりながら、「ヴェーバーとその時代」に関する秀逸な歴史書となった。 本書では、ヴェーバーの著作・刊行史料はいうまでもなく、夥しい未公刊の一次史料が駆使されている。浩瀚な本書の土台は、研究室でのテクスト分析だけでなく、ドイツ、オーストリアを始めイタリア、ポーランド、ロシア、フランスなど28カ所もの文書館で史料渉猟にあたった今野氏の歴史家としての努力によって築かれたものである。 なかでも、「ローマ帝政期」など少年期のヴェーバーが遺した歴史作文の掘り起こしを含む第一章「政治的人格の形成」、フリードリヒ・ナウマンとの交友関係や闘病期における政治方針の一貫性などを述べた第二章「プロイセン・ユンカーとの対決」、さらに「独立自尊の人間を求める」ヴェーバー官僚制論の「原体験」ともいうべき生々しい官僚とのやりとりを描く第三章「ドイツの人間的基礎への批判」など、本書で初めて詳しく取り上げられた論点も多く、本書が今後長く参照されるべき一冊であることに疑念の余地はなかろう。 たしかに本書には、著者の若さ故か、断定的で独善的な筆致が散見され、先行する我が国のヴェーバー研究の参照度にも若干の不足が感じられる。しかし、このような欠点は、本書の全体的な価値を損なうものではない。本書に示された今野氏の圧倒的な筆力と堅固な知的胆力は、今後いっそうの研鑽を積むことによって、ドイツ史研究のみならず、広く学際的ドイツ研究に多大な貢献を果たすことを確信させるものである。 以上の理由から、日本ドイツ学会奨励賞選考委員会は、本書を奨励賞受賞に相応しい作品と判断した。 |
|
|
今野元氏の受賞のあいさつ 愛知県立大学外国語学部ドイツ学科の今野元でございます。本日は名誉ある賞を頂きまして、大変な光栄に存じます。 私が大学に入学しましたのは、ドイツ再統一の興奮醒めやらぬ1991年のことでして、ナショナリズムの再来が世界中で脚光を浴びた時期でした。世間は分断を克服したドイツへの祝福で溢れていましたが、大学の教壇では再燃したドイツ・ナショナリズムを遺憾とし、ヨーロッパ統合の進展に期待するという論調が支配的だったように記憶しています。そうしたなかで、人権、デモクラシー、理性といった知性主義的な理想と、ナショナリズムのような人間の情念との相克という現象に興味を抱いた次第です。 私が大学院時代に課題としたマックス・ヴェーバーは、そうした好奇心に十分に応えるものでした。ヴェーバーは確かに傑出した知識人で、親英米の立場でドイツの政治的近代化を目指しましたが、同時に決然たるドイツ・ナショナリストでした。紋切型の反西欧的ドイツ・ナショナリストではなく、また無邪気な西欧礼讚者でもない、西欧派ドイツ・ナショナリストであるところに、ヴェーバーの特徴があります。彼の政治的言動は、ヴォルフガング・J・モムゼン以来歴史研究の対象とされてきましたが、私が先行研究に付け加えたものが多少あるとすれば、知性主義的な政治観には、ナショナリズムのような情念を抑制する面と、逆に助長する面とがあるという点でしょう。 私は政治学とは、人間同士がいかに共存しうるか、あるいはできないかを考える営みだと定義していますが、そこで大事なのは、そもそも人間とはどのような存在かを見据えることだと思っています。この著作でも、ドイツ・ナショナリズムという大きな問題を扱うに際し、ヴェーバーやその同時代人の人間性を見詰めるところから出発しています。ただ今後分析対象が変わり、周囲の社会環境が変わると、あるいは私の人間観にも変化が生じるかもしれません。私は今後、近世から現代までの幅広い分野で、引き続きドイツを舞台に人間の共存について考えていきたいと思っておりますので、ご列席の先生方には今後ともご指導ご鞭撻を頂戴できますと幸甚に存じます。 昨今は学問を取り巻く環境が変わり、実学ばかりが強調されるようになって、(とりわけ歴史・思想・文学・言語分野の)ドイツ語圏の研究は容易ならざる状況にあります。英米圏の研究や発展途上地域の研究、とりわけ流行のアジア研究なども重要ですが、欧米世界の重要な一要素であり、近代日本とも縁が深かったドイツ語圏の研究が、その意義を失うことは今後とも有り得ないと思われます。その意味で、その牽引車であり、学際的討論の場である日本ドイツ学会の益々のご発展をお祈り申し上げる次第です。私もドイツ政治担当の一教員として大いに勉強させて頂き、学生にドイツ学の面白さを伝えるべく努力して参りたいと存じます。 |
|
|
2006年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
の二点に授与することが決定されました。2007年6月23日、東京・明治大学において開催された日本ドイツ学会学術総会に際して、授賞式が行われ、学会奨励賞選考委員会の木村靖二委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会広渡清吾理事長から宮本直美氏と山口庸子氏に賞状と副賞が手渡されました。授賞式では、両氏から受賞にあたっての挨拶がのべられました。 |
|
選考理由 宮本氏の研究は、19世紀以来のドイツ社会を特色づける教養市民層の検討の切り口として教養理念そのものを対象に取りあげ、その際教養としての音楽の成立・拡大・浸透過程からを教養市民層の輪郭を浮かび上がらせるというユニークな手法を採用している。個々の部分では先行研究の問題提起や成果を踏まえているが、とりわけ2章・3章アマチュア音楽活動とオラトリオブーム、バッハ復興運動などは、きわめてオリジナリティの高い分析で、説得力も高い。もっとも、教養理念の「規定不能性」と本書で強調されている指摘は、例えばマンハイムが19世紀保守主義・自由主義について、それが具体的な主義・政策を意味するものではなく、本質的には「Haltung」であったとしていることから、教養だけに限定されるべきかは疑問無しとしないなどの点もあるが、全体としては意欲的挑戦として評価できる。 山口氏の研究は、これまでほとんど体系的検討がなされてこなかったモデルネ期の舞踏に焦点を当てたもので、それらを担う有名・無名の群像の分析からモデルネの舞踏、「踊る身体の詩学」のアンビバレントな性格、革新と危うさを描き出している。特に序章は歴史学・社会学その他この分野に関わる研究者に新しい視野と示唆的な問題提起を含む内容であり、3人のユダヤ系女性詩人を扱った第3部も印象深く読める。長年の研鑽の成果をまとめたものであることから、内容的にやや一貫性を持って理解しにくいところが散見されるが、当該分野でだけでなく、ひろくドイツ関連分野の裨益するところに多い業績である。 |
|
|
宮本直美氏の受賞のあいさつ 立命館大学の宮本直美と申します。本日は、大変光栄な賞を頂きまして、誠にありがとうございます。ご連絡を頂いた時は、非常に驚きましたし、少々当惑も致しました。 |
|
|
山口庸子氏の受賞のあいさつ 名古屋大学国際言語文化研究科の山口庸子です。このたびは、日本ドイツ学会の奨励賞を賜り、誠にありがとうございました。非常に驚きましたが、とても嬉しいお知らせでもありました。日本ドイツ学会、および選考委員の先生方に、心から御礼を申し上げます。また、著書が完成するまでの長い執筆期間に、ご助力と励ましとを頂いたすべての方々にも、この場を借りて御礼を申し上げたいと思います。 |
|
|
2005年度日本ドイツ学会奨励賞は、学会奨励賞選考委員会による慎重な選考を経て、
に授与されました。2006年6月10日、京都・立命館大学において開催された日本ドイツ学会学術総会に際して、授賞式が行われ、学会奨励賞選考委員会の木村靖二委員長から選考経過と受賞理由の発表があり、日本ドイツ学会広渡清吾理事長から藤原辰史氏に賞状と副賞が手渡されました。授賞式では、藤原氏から受賞にあたっての挨拶がのべられ、受賞した作品のモチーフが披露されるなど、意義深いスピーチでした。 |
|
選考理由 藤原辰史氏の研究テーマは、ナチズムと自然保護、エコロジーとの密接な関係がもつ意味を、有機農業、とりわけ「バイオ・ダイナミック農法」の展開とナチスの農業観との融合を事例として分析することで、解明しようとするものである。 |
|
|
藤原辰史氏の受賞のあいさつ 藤原でございます。京都大学の人文科学研究所に勤めております。このたびは、日本ドイツ学会奨励賞をいただきまして、しかも今回が第一回ということで、大変光栄に存じます。日本ドイツ学会の選考委員の先生方にこの場をかりて心より御礼申し上げます。 |
  |
今年度日本ドイツ学会奨励賞候補作品募集のお知らせはこちら